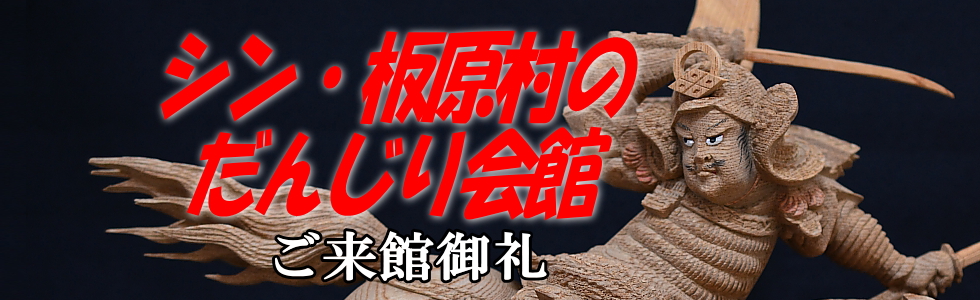先日の日曜日。
4年ぶりに開催されたという田尻町のふれあいイベントで、自身初めての見学となりました嘉祥寺のだんじりと、吉見のやぐらをレポして参りました。
ってなわけで、早速ご覧いただきましょう。
どうぞ。。
まずは嘉祥寺のだんじりから。

◆嘉祥寺地車◆
製作:昭和7年
●大工:【絹屋】絹井楠次郎
●彫刻:田沼源治(責任者)、玉井行陽(助)、松田正幸(助)
●エピソード
かつて朝鮮で暮らす日本人街向けにと、海を渡る予定だった地車。
しかし事情により破談となり、倉庫で保管されることに。
同じ時期、当町青年団からの要望もあり購入に至ったという。

▲前後の姿見です。

▲主屋根正面
昭和62年の吉為工務店での大修理では、現在のような扇垂木ではなくカチコミ垂木を施していた。(当時の吉為工務店で修理した和泉市小田町・堺市豊田の地車も同様にカチコミ垂木の細工)
平成20年には大下工務店で扇垂木に。
そして令和4年、大真工務店での大修理を経て現在に至る。


▲主屋根左右の木鼻
あっさりと嫌味なしの秀作です。

▲隅出すには牡丹に親子唐獅子。

▲鬼板
均整の取れた美しいシルエット。

▲主屋根左平の桝合「本能寺の変」
後屋根正面桝合によく見る図柄ですが、主屋根平には珍しいかも。
よう彫られてますね。

▲縁隅木には「嘉」の文字。
腰回りは、彫刻責任者の田沼源治師ワールド全開!!

▲まずは正面土呂幕「本多出雲守と荒川熊蔵の一騎討ち」

▲続いて平右「槍の名手・後藤又兵衛」

▲同じく平左はおなじみ、「加藤清正と新納武蔵守の一騎討」

▲左右の松良をそれぞれ平方向から。
昭和62年の大修理で新造されてます。
淡路風の秀作。筒井さんの作かな?

▲竹の節は個性的でした。
波に千鳥。これは唯一無二かも。
物見と一体感があるのもいいですね。

▲海に近い町らしい意匠。

▲では見送りを見てみましょう。


▲見送り内には、田沼師以外の手が入ってることが分かります。
淡路の巨匠のほか、昭和62年の大修理で加えられた作品も…。

▲大脇は玉井行陽師のようですね。

▲後屋根桝合正面には「曽我五郎大磯驀進」。
手には槍を持たせてますが、もとは大根であったかと…。
では続いて吉見のやぐらです!

◆吉見 (やぐら)
製作:平成4年。比較的新しいやぐらですね。
●大工:川端建設
●彫刻:木下彫刻工芸

▲前後の姿見です。
やぐらの知識は乏しい私は、どこから見ていいのやら…。

▲主屋根正面の獅嚙み
泉南地方のやぐらは、箕甲を噛まず上に乗っている感じです。

▲柱芯の間隔が狭くスリムな印象。

▲主屋根枡合平右「酒呑童子退治」

▲幕板平右「頼朝の朽木隠れ」

▲後屋根幕板 後方より向かって左平「巴御前の勇戦」

▲二輪のやぐらの足回り。
だんじり地域の私には興味津々で。。

▲後屋根幕板 後方より向かって右平「義経の八艘飛び」

▲主屋根幕板 平右「木曽義仲」

▲主屋根桝合左平「頼光の木渡り」

▲規則正しく配された組物は、六手先七段。
柱芯の列と隅出す・横槌は全て尾垂木。

▲正面・平とも桁の全てに、千鳥の「隠し」が配されてました。

▲獅噛の二丁撮り、個人的には好き♪

ということで、長編におつきあい頂きありがとうございました。
自身、久しぶりのレポ。
シン・板原村では、初のレポとなりました。
また気持ちを充電して、レポに挑みたいです。
さて、次はどこのだんじりかなぁ~。
あぁ疲れた。今宵はこれにて。