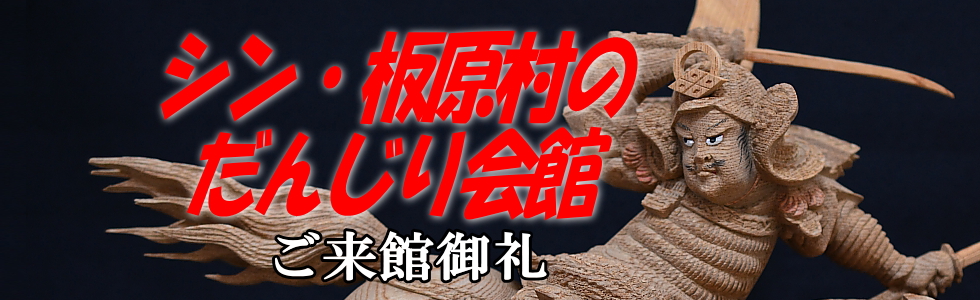9月28日(日)
早いもので、9月も最後の日曜日となりました。
今日は南海電車を利用し、まずは泉佐野で下車「ザ・まつり」見物と、貝塚えきに移動して麻生郷の試験曳を見物して参りました。


泉佐野駅に着いたのは正午前。
駅下の居酒屋でちょいと一杯、ほろ酔い気分でパレード地点へ。
すでにスタートを待つ7台のだんじりと1台のやぐらが揃っていました♪

この泉佐野には、明治・大正・昭和・平成と、それぞれの年代で製作されただんじりが揃うという、ファンには嬉しい地区。




人混みに悩まされることなく、比較的ゆっくり拝見することができました。
そんな自由気ままなほろ酔いレポですが、ご覧ください(笑)。。。


鶴原東の松良!
名匠・岸田恭司師の作と思われる作を発見♪

で、やりまわしも最前列で♪




鶴原地車
製作:大正11年
大工:田端辰次郎(大弥三)
彫刻:一元林峰
当町新調、一元林峰師の持ち味が存分に表現された一台。

平成12年新調の上瓦屋地車。
岸和田の老舗、植山工務店(植山良雄)と、彫師は岸田恭司師&近藤晃師のコンビによる大型だんじり。
詳しいだんじりレポは、過去の記事をご覧ください!
こちら↓
泉佐野・上瓦屋地車 | 板原村のだんじり会館

やぐらで唯一参加の岡本町。
新調:昭和11年(平成5年尾崎宮本町より譲受)
大工:辻幾次郎
彫師:開生珉、宮沢巌
開さんの彫刻までは確認できず…もっとじっくり拝見すべきでした(反省)。



右:下瓦屋南
明治20年ごろに岸和田市大北町新調→熊取町小谷区→当町
左:下瓦屋(北出)
大正8年に当町新調。昭和32~50年は休止。熊取町の個人→岸和田市磯上(大道町)
→岸和田市内畑町下出→当町(生まれ故郷へ里帰りとして話題に。)
大工:絹井楠次郎(絹屋)
彫師:玉井行陽


下瓦屋南地車は、元・岸和田市大北町の先々代ということで、随所にその名残を垣間見ることができる貴重な1台。


鶴原新家地車
経路:昭和8年頃に岸和田市山直地区の某所が新調か?
昭和12年頃に絹井楠次郎(絹屋)を介して貝塚市窪田が購入。平成15年に貝塚市窪田より有志が購入、実に約50年ぶりの復活。
大工:絹井楠次郎(絹屋)
彫師:玉井行陽

主屋根正面枡合いには「大江山」と思われる彫刻。



土呂幕は「朽ち木隠れ」でしょうか。
絶妙の雰囲気は、さすが玉井行陽師!

中之庄地車。
昭和11年 岸和田市福田町が新調。泉佐野市大西町を経て昭和37年に当町が購入。
大工:植山宗一郎(大宗)
彫師:吉岡義峰(京彫)
昭和7年から8・9・10・11年と連発して新調だんじりを世に送り出している大宗こと植山宗一郎さん。
そのシリーズは微妙な変化があるものの、同系列として共通する箇所が多く見ていて楽しくなります。


1時間半ほど見物し、泉佐野から貝塚へ移動。
駅では「ミャクミャク ラピート」に遭遇♪

ということで、南海電車で移動し貝塚駅で下車。
駅前では多くの人だかりで、次々にだんじりがやってきます。



麻生郷地区のだんじりは、どれも大型ばかり。
豪華な新調だんじりから、あの淡路彫りの舜さんや京彫りの義峰さんまで…。



最もお目当ての東地車!
やっぱり格別です!かっこいい♪

半田町地車

石才町地車

久保町地車

小瀬町地車




東町地車
彫刻は淡路彫り・木下舜次郎師の最高傑作として名高い。


おまけ:大学時代の後輩、久保町のだいすけ。
平成30年(私が若頭会長の年に)板原町常纏を新調。その際、大工職人の彼に、纏台を依頼して作事していただいた経緯があります(笑)。
だいすけ、元気そうでよかった♪

ということで、貝塚をあとに泉大津へ。
泉大津駅では旧南海カラーの7100系が停車中でした。
左には、泉佐野で見たミャクミャクラピートに2度目の遭遇(笑)♪
という、1日でした。
ではまた。