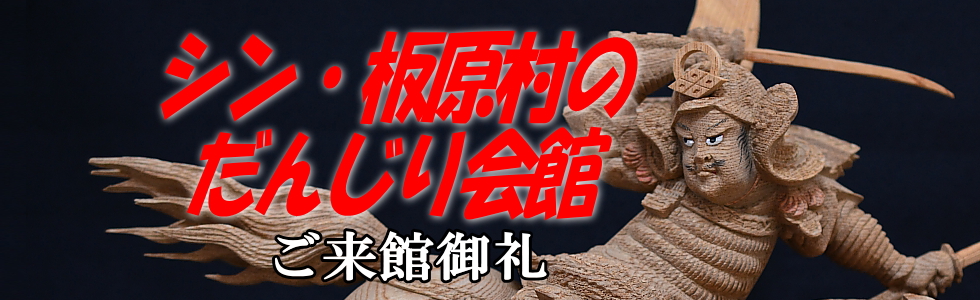令和7年5月11日(大安吉日)快晴
やっとこの日が来ました。
ずっと彫陽を応援してきた私にとって、待ちに待った晴れの日。
泉州にまた1台、歴史に残る銘だんじりが誕生しました。
貝塚・森町の新調地車。
大工棟梁は、自町内に店を構える横井工務店の横井光造さん。
彫刻責任者は、筒井・岸田両師の技を受け継ぐ彫陽こと山本陽介さん。
共に「出世作」という、誠にめでたいコンビで作事されました。
私はというと、単身赴任の身なので月に1~2回の帰省をしており、GWの帰省からわずか数日で再び泉州へとんぼ返りし、この晴れの日の取材に駆けつけました…。
午前3時50分に、泉大津の自宅を出て目指すは貝塚・森町。
そんな様子を、まずは前編でご紹介します。
どうぞ~!


午前4時30分森町内。
関係者様から許可をいただき指定された駐車場に停める。



横井工務店さんへ向かう途中、ライトアップされた「先代」を少し拝見。
植山春松さんが作事された希少な1台。


太鼓の音に導かれ横井工務店さんへ向かっていると「館長さん!こっちへどうぞ!」と暗がりで声をかけてくださった森町内のKさん。
初っ端から親切なKさんに感謝。いい入魂式になること間違いなしの予感。

いきなりの平の姿見から!!
嫌味なし、あっさり古風で、格好ええ~!!
この日初めて新調だんじりを捉えた写真がこちら。

彫陽の陽ちゃん、お弟子さんの中村くん、陽ちゃんの奥様、3人でおめでとうございます!!の話をしていると、にわかに騒がしくなる。おぉ~!出発や!!慌てて店先に出る(汗)!!






軽やかに、曳きだし太鼓で小さな坂を駆け上がり
新しい地車庫へ向かう。
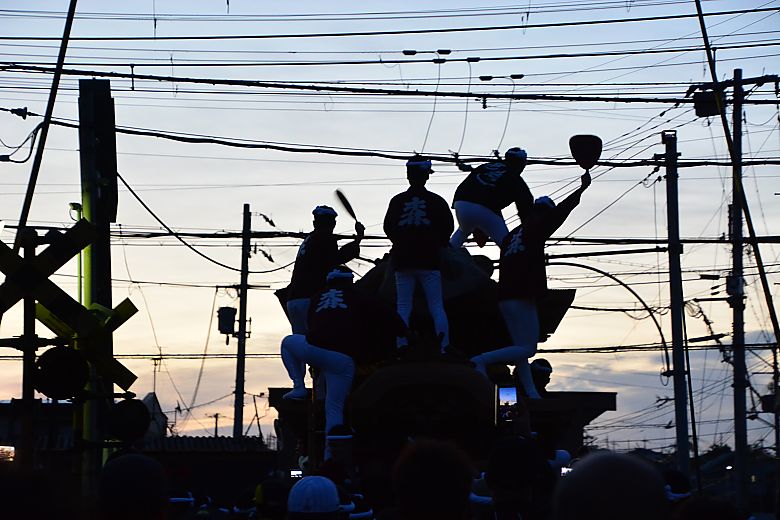
陽が昇ってきました。



水間鉄道の線路脇にある新築の地車庫へ到着。




後ろ幟・吹きちりを付け、宮入の準備です。
ここでもしばし町内の方とお悦びの雑談。
















社殿では清祓いの祝詞があげられている中、完成仕立てのだんじりを見物します。

「宮本」の誇らしげな2文字。


梃子掛け・ねこ木に稲穂。


破風、ひな壇にも稲穂。

三手先七段という飽きの来ない、古風で嫌味のない姿見。
これが横井工務店さんの「横井型」になりそう。



懸魚といえば筒井師のもとで修業を積んだ陽介師ならではの作風。
非の打ちどころなしの作。

正面腰回り。
彫刻細部については、後日改めて…。


正面左右の松良受けは鯉。



この地車の最大の特徴でもある枡合いの細工。
三手先七段ゆえに、広く大きく木取りされたキャンパスは、迫力満点。
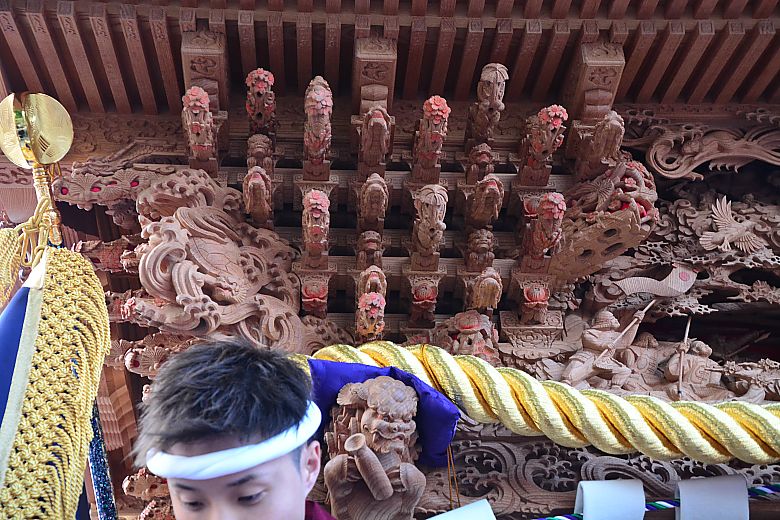
大振りの組み物と繊細な細工。
垂木間隔も、三手先ならでは。

脇障子竹の節、兜桁。


見送り下の隅木も独特の細工。
欠損しないか心配になるほどの繊細さ。


後屋根は平の柱芯、菖蒲桁から徐々に開く「隅掛け扇垂木」。
隅木受けは松の細工。岸和田型地車では珍しい!!


左:主後の懸魚。
右:後屋根懸魚。



土呂幕には、陽介師十八番の巴御前。
この雰囲気は親方・岸田師譲りの傑作。
今回、すべての人物・馬などの瞳に瞳孔をひとつひとつ丁寧に書き入れた陽介師。
彼の几帳面さが伺える。






そろそろ出発の時間のようです。。



さぁ!清祓いも済み、お披露目曳行です!



恰好よろしいなぁ~。







宮出から一発目のやりまわしを見ようとしていると
ここでも町内の方に「館長さん~ここでいとき~!」と親切にしていただきました。
前編はここまで。
快心のやりまわしは、後編で♪
ではまた。